ドラマもしがく「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」一度聞いたら忘れられないこのドラマ、一体どんな物語なのか気になりますよね。原作は漫画?小説?脚本家は?
2025年夏、三谷幸喜が25年ぶりに民放連続ドラマに帰ってきました。
タイトルは『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』略して「もしがく」。この記事では、そんな疑問をまるごと解決!ストーリーの舞台や時代背景、豪華キャストの情報も含めて、三谷ワールドの魅力をたっぷりご紹介します。
#三谷幸喜 25年ぶり民放GP帯連ドラ脚本!
— 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』【フジテレビ公式】 (@moshi_gaku) September 2, 2025
主演 #菅田将暉
共演 #二階堂ふみ #神木隆之介 #浜辺美波
1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、
若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像!
「もしもこの世が舞台なら、
楽屋はどこにあるのだろう」
10月1日(水)よる10時スタート#フジテレビ#もしがく pic.twitter.com/4SG4cSR8Cn
もしがくの原作はあるの?漫画や小説は?
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』には、原作となる小説や漫画は一切存在しません。これは、完全オリジナルのストーリーで構成された作品です。最近では人気コミックや小説をドラマ化する傾向が強く、原作ありきの作品が多い中で、オリジナル脚本というのは珍しくもあり、制作側の強いこだわりが感じられます。
本作の脚本を手がけたのは、言わずと知れた三谷幸喜さん。三谷さん自身がこのドラマを「僕にしか書けない物語」と語っており、まさに彼の頭の中から生まれたオリジナルの世界観となっています。原作がないからこそ、視聴者はネタバレなしで毎週の展開を楽しみにでき、俳優の演技や脚本の緻密さに集中することができます。
また、原作が存在しないということは、登場人物のバックボーンやセリフのひとつひとつに、脚本家の意図が強く反映されているということ。三谷作品においては、会話のテンポや人間関係の妙が見どころでもあるため、オリジナル作品だからこそ生きる要素が満載です。
これまでに多くの三谷作品を観てきた人なら、その世界観の深さやユーモアのセンスにすぐ気づくはず。初めての人にとっても、新鮮で知的な物語体験になること間違いなしです。原作がない、というよりも、「これ自体が原作になり得るドラマ」と言えるでしょう。
脚本は三谷幸喜!25年ぶりの民放GP帯連ドラ復帰
本作の最大の注目ポイントのひとつが、脚本を担当するのが三谷幸喜さんであるという点です。三谷幸喜さんは『王様のレストラン』『古畑任三郎』『合い言葉は勇気』など、数々の名作を生み出してきたヒットメーカー。今回のドラマは、三谷さんにとって25年ぶりの民放・ゴールデンプライム帯連続ドラマになります。
「え、25年ぶり!?」と驚く方も多いかもしれません。実は、三谷さんはこの長い間、舞台や映画を中心に活動しており、テレビドラマの脚本からは距離を置いていました。それだけに、今回の復帰作にかける意気込みは相当なもの。本人も「今の自分だからこそ描ける作品」と語っており、これまでのキャリアを総動員した意欲作であることが伝わってきます。
三谷幸喜作品といえば、独特のユーモアと皮肉、そして人間臭さが絶妙にブレンドされた脚本が特徴です。一見すると軽妙な会話劇ですが、その裏にある深い人間ドラマや、時代性を反映したテーマが胸に残ります。今回の『もしがく』(略称)は、1980年代の渋谷を舞台にした青春群像劇。時代設定や空気感をどう表現するか、三谷節の真骨頂が楽しめる内容となりそうです。
久しぶりのテレビドラマ復帰となる三谷幸喜さんが、どのように現代の視聴者に物語を届けるのか。その“再始動”に、業界内外からも大きな注目が集まっています。
ストーリーの舞台と設定:1984年・渋谷の劇場群像劇
『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の物語は、1984年の渋谷を舞台に展開されます。当時の日本は、高度経済成長を経てバブルの直前。街には夢や希望、そして不安や焦燥が入り混じっていました。そんな時代の渋谷を背景に、劇団に所属する若者たちの人生と葛藤を描く青春群像劇です。
劇団と聞くと、夢を追う若者たちのキラキラした日常を想像するかもしれませんが、三谷さんの描く物語はそう簡単にはいきません。誰もが何かにくすぶっていて、成功したいのにうまくいかない。仲間を大切にしたいのにすれ違ってしまう。現代にも通じる“人間の弱さと強さ”が、1984年という時代設定を通して描かれます。
また、三谷幸喜さんは自身も若い頃に劇団活動をしていたことから、このドラマには半自伝的な要素も含まれていると言われています。劇団という舞台の裏側、人間関係、演劇にかける情熱など、彼自身の経験が作品にリアルな説得力をもたらしているのです。
特に注目なのは、“舞台”と“楽屋”という二重構造の象徴的なタイトルです。これは「人生が舞台ならば、私たちはどこで本音を吐くのか?」という問いかけでもあります。自分を演じながら生きる現代人にとって、この問いはどこか胸に刺さるものがありますよね。
注目の豪華キャストとスタッフ情報
このドラマが話題になっている理由のひとつは、超豪華なキャスト陣です。主演は菅田将暉さん。演技力と存在感に定評のある彼が、三谷作品に初挑戦することでも注目されています。共演には、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さんといった若手実力派が勢揃いし、まさに“演劇界のドリームチーム”とも言える布陣です。
演出を手がけるのは西浦正記さん(代表作:『教場』『コード・ブルー』など)。プロデューサーは金城綾香さんと野田悠介さんで、どちらもフジテレビの看板ドラマを多く手がけてきた敏腕スタッフです。脚本×キャスト×演出、どれを取っても最強クラスの布陣となっています。
このメンバーがひとつの作品に集結するというのは、それだけで特別な出来事。三谷作品の演出にはアドリブや即興的なやりとりが求められることも多く、キャストの演技力が問われる場面も多そうです。特に舞台が“演劇の世界”ということで、役者たち自身が“俳優としての本質”を問われる場面も出てくるかもしれません。
俳優陣の化学反応がどう表れるのか、脚本の世界観と演技がどう交わるのか。すべてが見どころとなる構成です。
なぜ今、このオリジナル青春群像劇なのか?時代的・文化的価値
本作が“今この時代に”制作されたことには、大きな意味があると考えられます。三谷幸喜さんが描く1984年の渋谷という舞台は、バブル時代の直前という“希望と不安が混ざった時代”でした。そして現代の日本もまた、閉塞感や格差、夢が持ちにくい社会背景があります。そうした時代と時代が交差する物語が、今だからこそ必要とされているのです。
また、最近のドラマや映画は、既存の作品をもとにした“原作ありき”が主流です。しかし『もしがく』は、オリジナルだからこそできる自由な発想で、登場人物たちの心理や背景を深く描いています。そこには、表面だけではない人間の“本音”や“矛盾”が込められており、観る者の心に静かに問いを投げかけてくれます。
タイトルにある「楽屋」とは、人生の裏側=心のよりどころを意味するのかもしれません。誰しもが「楽屋」を持ちたいと思いながら、それがどこにあるのかわからない。そんな現代人の孤独や希望が、1984年の演劇青年たちの姿を通して浮かび上がってきます。
今の視聴者にこそ響くこの物語は、「オリジナル作品」の意義を再確認させてくれると同時に、“人が生きるということ”をそっと描き出す、三谷幸喜ならではの名作になる予感がします。
まとめ
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、原作なしの完全オリジナル脚本で、三谷幸喜さんの25年ぶりの民放連ドラ復帰作として大きな注目を集めています。物語の舞台は1984年の渋谷、劇団に所属する若者たちのリアルな葛藤と夢を描いた青春群像劇です。
原作が存在しないことで、展開の予測がつかず、視聴者は毎週新鮮な驚きを楽しめます。また、菅田将暉さんをはじめとする実力派キャストが勢ぞろいしており、演技の掛け合いや人間ドラマの深みも見逃せません。
「舞台」と「楽屋」という二重構造のテーマは、今を生きる私たちにも通じる深いメッセージを投げかけてきます。観終わったあとに、自分自身の「楽屋」がどこにあるのか、ふと考えてしまうような、そんな温かくて鋭いドラマになりそうです。
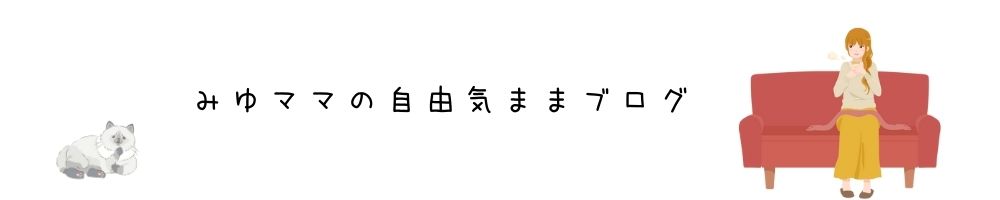
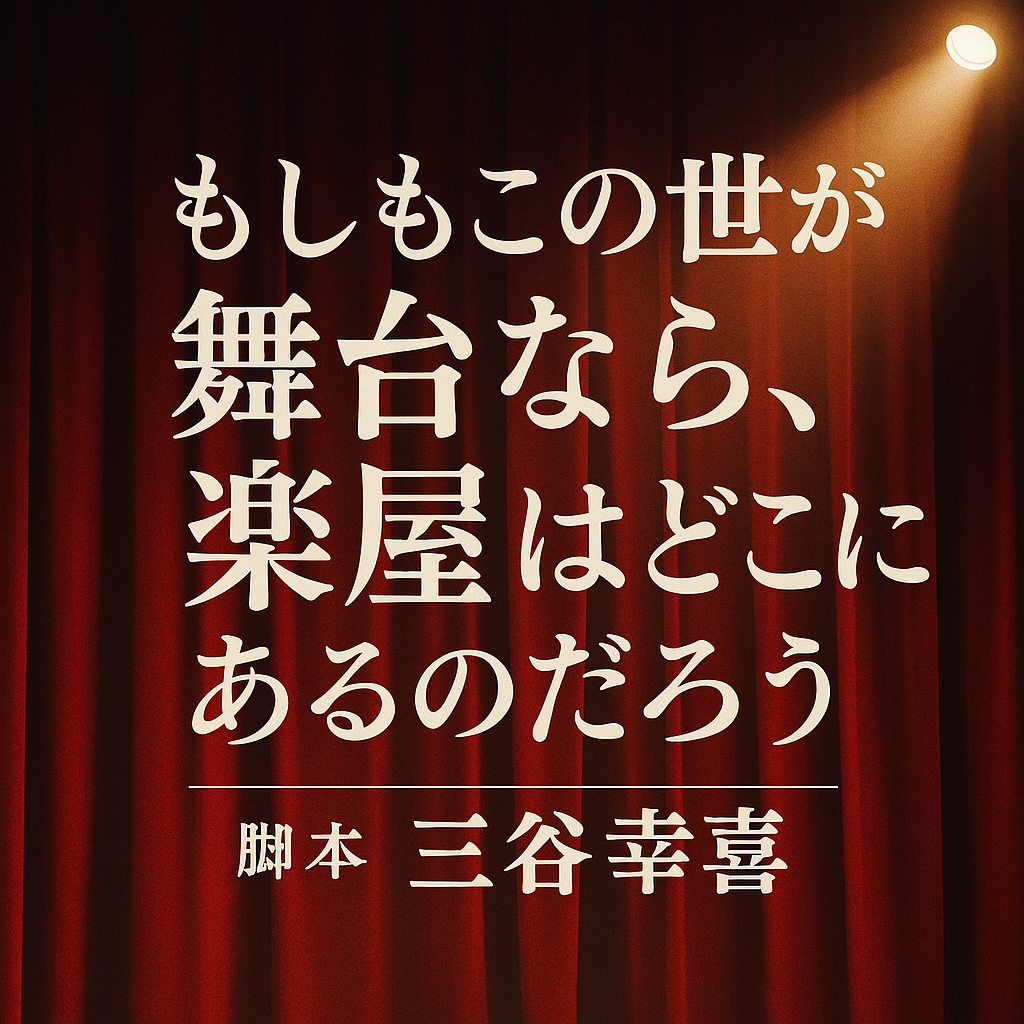
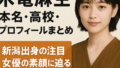
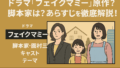
コメント